AWS、開発スキルがなくても生成AIへのプロンプトで業務アプリが作れる「AWS App Studio」プレビュー公開
Amazon Web Services(AWS)は、生成AIに自然言語で作りたい業務アプリを説明すると、自動的に業務アプリの開発が行われる新サービス「AWS App Studio」をプレビュー公開しました。
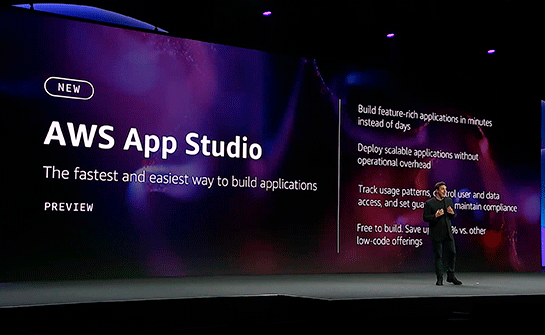 7月11日に開催されたAWS Summit New York City 2024でAWS App Studioが発表された
7月11日に開催されたAWS Summit New York City 2024でAWS App Studioが発表されたAWS App Studioはソフトウェア開発のスキルがなくとも、業務アプリケーションを数分で開発できるとしています。
生成AIにアプリを説明、要件や機能が自動生成
下記がAWSが公開しているデモ動画の画面キャプチャです。
トップページ。真ん中の黄色い枠に囲まれた「CREATE NEW APP」をクリックすると、新規アプリケーションの開発が始まります。
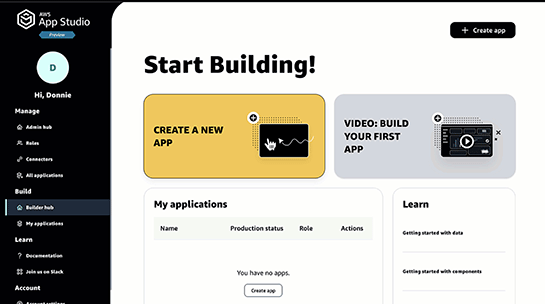
アプリケーションの名前を設定し、生成AIによる開発を選択。
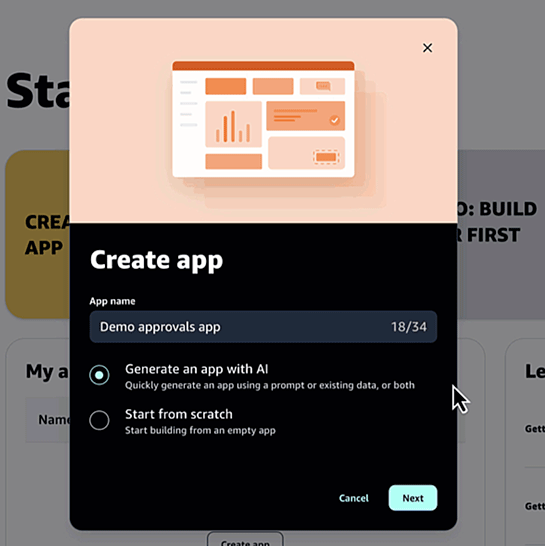
データソースを設定。データソースとしてAmazon Aurora、Amazon DynamoDB、Amazon S3、Salesforce、OpenAPIなどに接続可能なコネクタが用意されています。
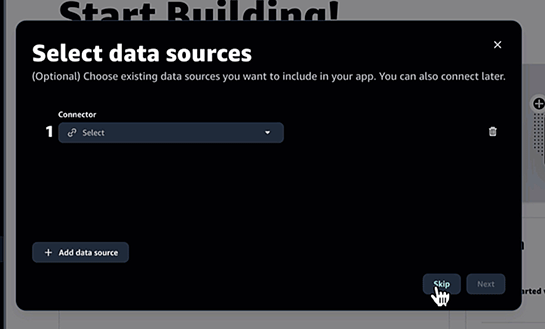
すると、生成AIとの対話画面となります。左側が、作りたい業務アプリケーションの内容をプロンプトとして入力する画面で、右側はサンプルプロンプトが数種類並んでいます。
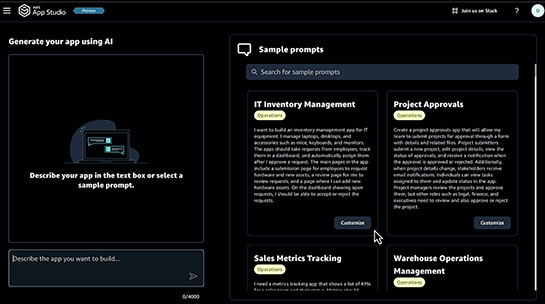
左側のペインに、作りたい業務アプリケーションの内容を説明するプロンプトを入力します。
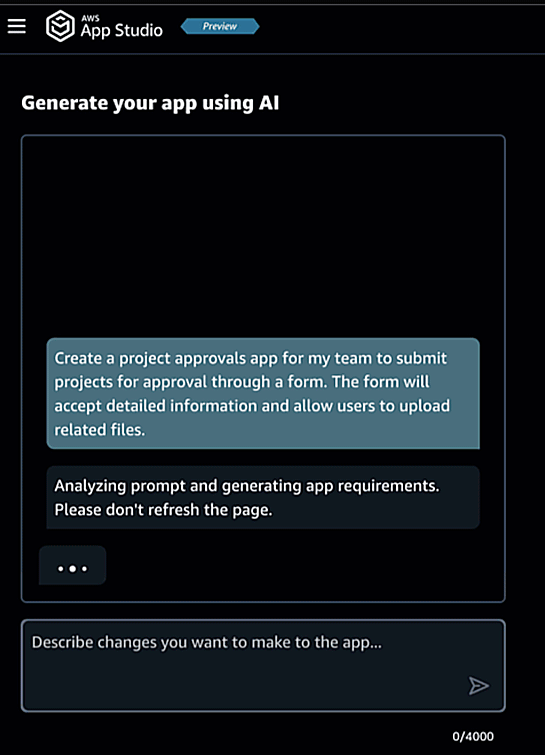
入力されたプロンプトを元に、生成AIがアプリケーションのユースケース、操作の流れ、主要な機能などを箇条書きで出力します。
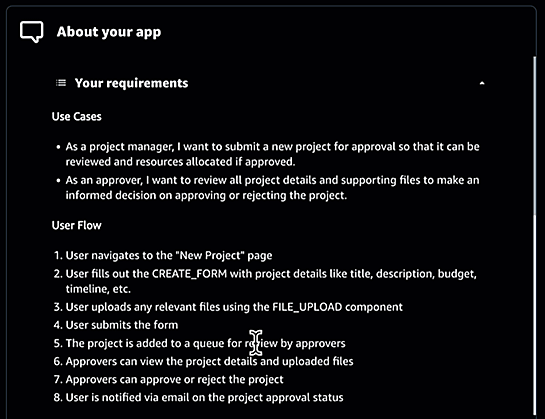
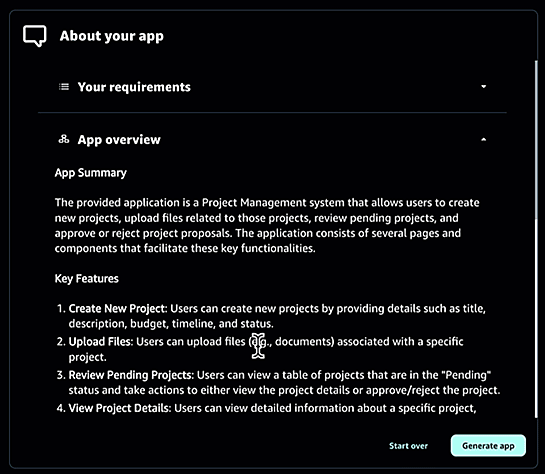
内容を確認して問題なければ、アプリケーションの生成を開始。
生成されたアプリケーションの画面設計、ビジネスロジックのフローなどを確認します。ビジネスロジックはAPIコールやAWS Lambdaなどによる拡張も可能とのこと。
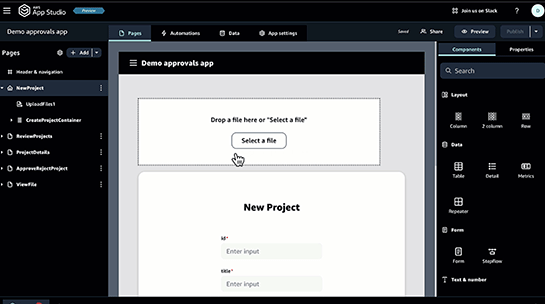
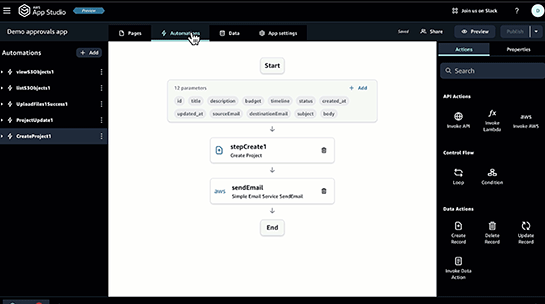
プレビューで動作を確認することもできます。
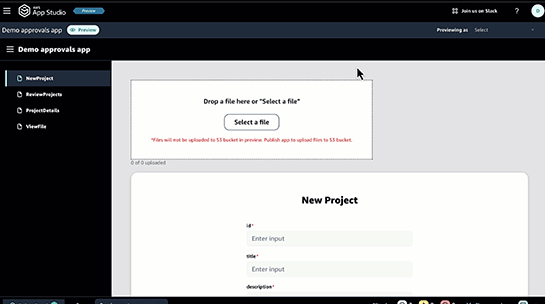
「Publish」機能により、テスト環境もしくは本番環境にアプリをデプロイできます。
AWS App Studioの利用料は無料
AWS App Studioの利用料金は無料で、料金は開発されたアプリケーションの使用時間に対して発生するとのことです。
GitHubは、生成AIに説明することでアプリケーションの開発が行えるGitHub Workspaceのテクニカルプレビューを4月に開始しています。
AWS App Studioは、このGitHub Workspaceの競合に位置づけられるでしょう。
参考:GitHub、「Copilot Workspace」テクニカルプレビューを開始。ほとんど全ての開発工程をAIで自動化
あわせて読みたい
Oracle Exadataをクラウド上のスケーラブルなソフトウェアとした「Exadata Database Service on Exascale Infrastructure」提供開始
≪前の記事
ESLintがJavaScript以外にも対応言語を広げるとの方針を説明。まずはJSON、Markdownへの対応プラグインを開発

