運用を見える化することでDevOpsを前進させよう(前編)~DevOps Day Tokyo 2013
世界中でDevOpsのムーブメントを広げているイベントDevOps Daysが今年も東京で「DevOps Day Tokyo 2013」として9月28日に都内で開催されました。
今年の主なテーマは「メトリクス、モニタリング、コラボレーション」です。開発と運用がツールとカルチャーによって協力するというDevOpsの基本を実現する上で、メトリクスやモニタリングは重要な手段です。それをどう実現するのか、具体的な紹介を行うセッションがいくつも行われました。
基調講演として行われたNick Galbreath氏のセッション「Making Operations Visible」もメトリクスの見える化をテーマにした内容でした。ダイジェストでその模様を紹介しましょう。
Making Operations Visible
Nick Galbreath氏。
Etsyのディレクターエンジニアリングをつとめた後、いまはIPONWEBというところで東京で活動しています。

昨年は継続的デプロイの話をたくさんしたのですが、多くの会社で「まだツールが足りない」「社風的にまだそこまではできない」という壁に当たりました。
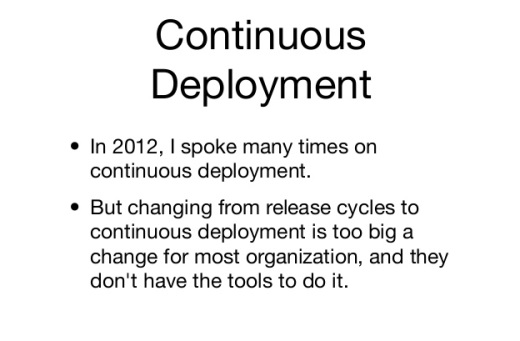
チームの外から見えないのは、存在しないのと同じこと
DevOpsは結局のところコミュニケーションだと思っています。しかし多くの企業ではツールやプロセスが社内の運用チーム以外の人から見えないという状況になっています。
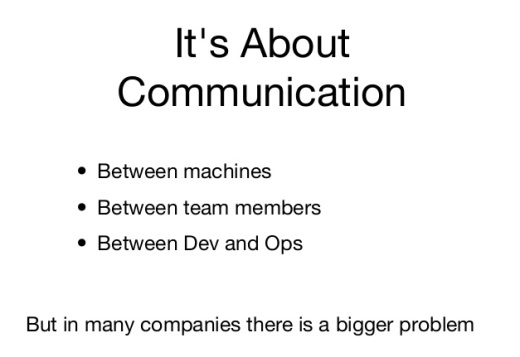
つまりそれは、みなさんが何をしているのか、ビジネス担当の側からはわからない、ということです。
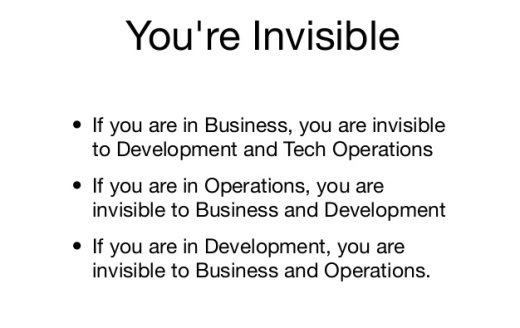
そして目に見えないものは価値がないものだと思われてしまいます。存在しないことと同じだということです。
多くの会社の開発者からも、自分のコードが本番運用環境でなにが起きているのかわからないという話をよく聞きます。だから「運用は運用チームにまかせておけばいいんだろう」とか、「なんでこんなに現場で問題が起きているのか、現場は何をしているのか」という話が出てくるのです。
ビジネス側からも、「なぜ月末にならないとデータがあがってこないのか」や、「先週やったリリースチェンジにはどんな意味があったのか」「なぜ運用担当者も開発担当者も、サービスの停止によってビジネスにどれだけ影響があるのか分からないのだろう?」といった声があがります。
でも運用では「こんなに忙しいのに、開発担当やビジネス担当はなんで面倒をかけてくるのか、もっとましな仕事はできないのか」と思っているでしょう。
一方で、運用担当者が会社のビジネスを理解していない、この会社はいったい何をしているのか? という状況もあります。ありえないと思われるかもしれませんが、本当に耳にすることなのです。
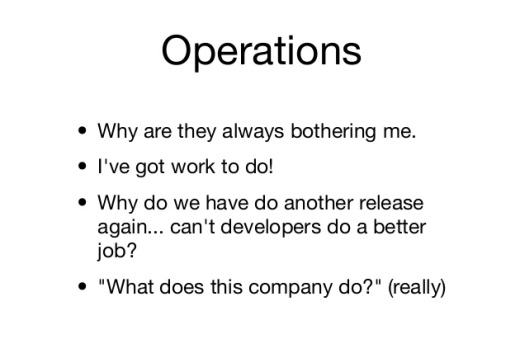
こうした状況は、運用担当者自身にとって破滅的なものだといわざるをえません。上司からどう評価されているのか分からないわけですし、同じことがチームにとっても会社にとっても破滅的なものだといえるでしょう。
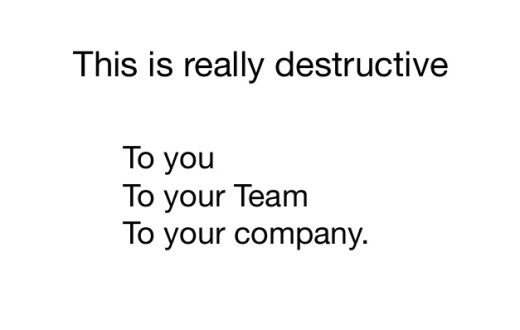
しかし会社の中にはたくさんのデータがあふれています。そうしたものを共有し、風通しのいいコミュニケーションができるようにすればいいのではないでしょうか。社内にあるデータを「見える化」していくことで、問題を解決していくことができます。
運用の見える化とは、運用だけを見える化するというものではなく、企業の運営そのものを見える化することなのです。
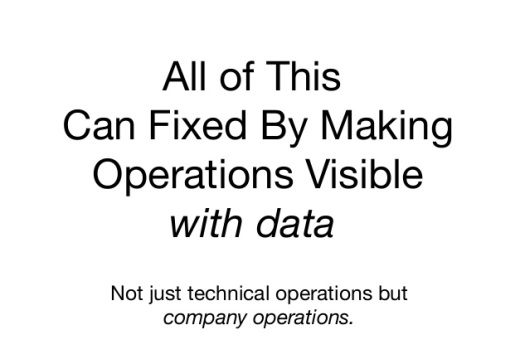
データを共有しない言い訳はたくさんある
しかし、こうした社内のデータを共有しない言い訳も実際にたくさん聞いてきました。
「グラフ作成機能なら、すでに自分の監視システムに備わっているよ」とか。でもたいがいの場合、データのマッシュアップも変換も共有もできなかったりします。
あるいは「どうせ見せても分からないから、共有する意味なんてない」と。実際には運用データをグラフ化すればほとんどの人は分かると思います。
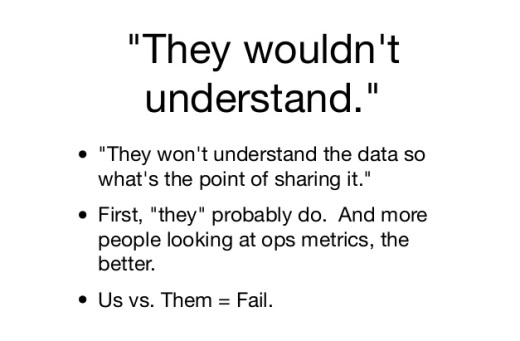
こうした、「われわれvsかれら」、という対立的な構造はよくありません。
「データが運用システムに入っているから、触ると壊れてしまう」という言い訳もあります。でも誰も意図的に自社の運用システムに入って壊す人はいないはずで、もっとまわりのひとを信用しなければなりません。
よくない言い訳として「これはあなたの仕事ではないのだから、知る必要はない」というのもあります。なぜ恐怖感にかられてデータを見せたくないのでしょう。
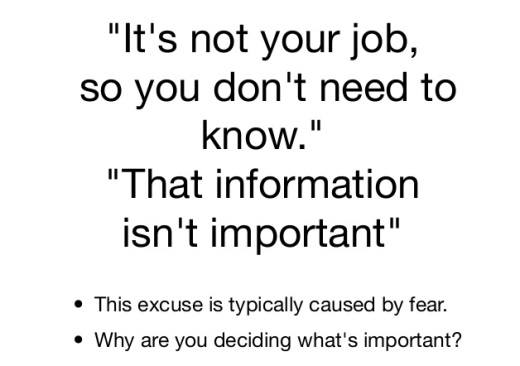
ほかにも「忙しいから」「危険だ」とか「どうやれば分からない」といった言い訳もあります。でも「やり方がわからない」というのは本当に問題ですから、一緒に解決していきましょう。
≫続きます。後編ではデータを共有するためのツールとしてGraphiteやStatsDなどが紹介されます。
DevOps Day Tokyo 2013
- 運用を見える化することでDevOpsを前進させよう(前編)~DevOps Day Tokyo 2013
- 運用を見える化することでDevOpsを前進させよう(後編)~DevOps Day Tokyo 2013
- GitHub社内のDevOpsを支えるツール「Boxen」と「Hubot」(前編)~DevOps Day Tokyo 2013
- GitHub社内のDevOpsを支えるツール「Boxen」と「Hubot」(後編)~DevOps Day Tokyo 2013
- クックパッドのインフラ責任者が語る、DevOpsを成功させる考え方「迷ったら健全な方を選ぶ」~DevOps Day Tokyo 2013
DevOps Day Tokyo 2012
あわせて読みたい
運用を見える化することでDevOpsを前進させよう(後編)~DevOps Day Tokyo 2013
≪前の記事
次バージョンのMySQL 5.7はさらに性能を2倍へ、「オラクルはMySQLを殺そうとしている」は真実ではない~MySQL Connect 2013

